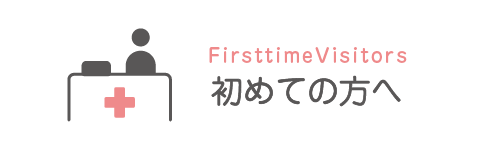白癬とはなんですか?
白癬は皮膚糸状菌という真菌の一種によって起こる主に皮膚表面の感染症です。皮膚糸状菌は、カビの一種です。ほかのカビと異なり、皮膚の表面の角質(ケラチン)を分解できる性質をもっています。
日本では白癬の原因菌として10種ほどの菌が知られています。その中で最も分離頻度が高いのが、トリコフィトン・ルブルムとトリコフィトン・インタージギターレ(メンタグロフィテス)です。
その他、格闘技の選手の間ではトリコフィトン・トンスランスというカビによる白癬も見られます。

白癬菌はヒトばかりでなく動物にも感染し、動物の種類によって感染する白癬菌も種類が異なっています。本来は動物に寄生する白癬菌が、宿主(動物の種)の枠を乗り越えてヒトに感染することがあります。代表的なものが、イヌ、ネコに寄生しているミクロスポルム・カニス(イヌ小胞子菌)というカビです。
なお皮膚糸状菌は白癬の原因菌であることから、白癬菌と呼ばれることがあります。
白癬菌はケラチンという蛋白を栄養源に生きているカビです。このケラチンは皮膚の表面を覆う角層(垢となって落ちる場所)、毛や爪の主要成分ですので、白癬は皮膚の表面に病変を作ります。粘膜にはケラチンが余りありませんので、口の中に白癬が生じることはありません。角質に菌が寄生し、増殖するとその過程でいろんな代謝産物を作ります。これが抗原になって皮膚に炎症を起こします。
白癬はどのように診断されますか?
白癬菌は皮膚の表面に存在する角層や毛、爪に寄生するので、白癬菌が寄生していそうな部位から検査材料をピンセット、メスの刃やハサミなどでとって、顕微鏡で観察します。診察室でスライドクラスの上で検査材料と苛性カリ(KOH)検査液をなじませ、顕微鏡で観察することで、早ければ数分で菌の有無が判定できます。この顕微鏡検査で白癬菌が見つかれば白癬です。見つからなければ白癬ではなく治療法も変わってきます。
白癬の治療には何があるのですか?
白癬の生じた部位、病変部の症状、基礎疾患や合併症により、治療には内服薬と外用薬が患者さんに合わせて処方されます。足白癬や体部白癬では皮膚の角層のみの感染ですので抗真菌作用を有する外用薬をきちんとつければ良くなります。しかし足白癬でも角層が厚くなっている角質増殖型と呼ばれる病型や、白癬菌が髪の毛や爪に寄生している場合は、外用薬では効果が不十分なことが多く、飲み薬による治療をお勧めします。
足白癬では、一見症状がない部分も含め、両足の足の指間から足の裏全体に、最低12週間毎日治療を続けないと治りません。1週間も塗れば症状は軽快してきますが、角質の中では菌が生存していることが知られていますので、治療中断後しばらくするとまた症状が悪化することもしばしばです。通常の足白癬であれば、塗り薬を毎日つければ、約1-2 週間程度で症状は良くなります。しかし2週間程度の外用では白癬菌は死滅し切らず、生き残っていることも知られています。しかし多くの患者さんは、自覚症状が消失すれば治ったと思い、治療を中止してしまいます。そのため翌年の夏には残っている白癬菌がまた増殖して、足白癬の症状が出てきます。また足白癬では、自覚症状のない部位にも白癬菌は存在します。しかし多くの患者さんは、水疱や痒みなど症状がある部位にしか塗り薬を使用しません。薬を自覚症状がある部分だけでなく、両方の指の間から足裏全体に最低1カ月毎日塗り続けることが大切です。
このように足白癬が治らない最大の理由は、中途半端な治療といえます。さらにきちんと塗り薬をつけて、一度菌が消失しても、同居している家族から、あるいは自分の爪に残っている病巣に由来する菌により再感染をおこす可能性もあります。